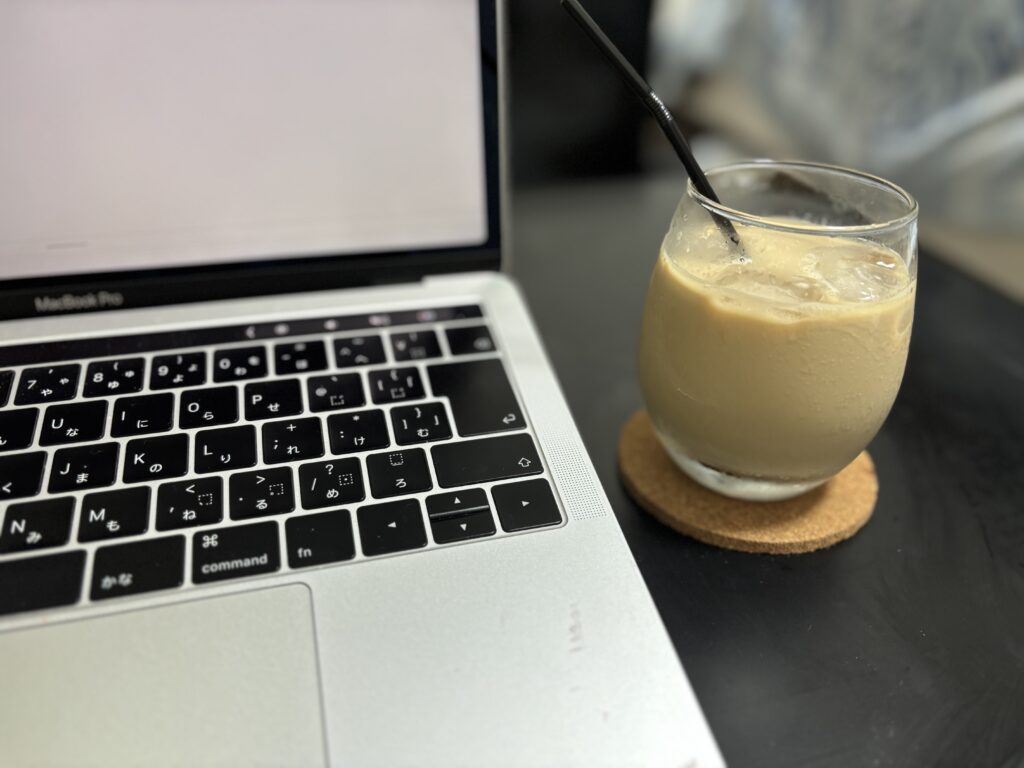
(別用途でコルク素材が欲しくてコースターを買った。)
部屋を片付けて一段落、というときに、「さて、ブログを書こう」と思った。
今日を過ごした自分の、頭の整理。
私にブログは向いているのかもしれないと感じる。
今日は何があった?そんなたいしたことはしていない。
チップスターの絵の続きを描いて、買いたいものがあったから百均に出かけ、
そこで見当たらないからと隣町に移動し、そこでも見つからずうなだれた。
予定にはなかったお茶屋さんにふらっと入り、店員さんに声をかけられ、
ちょっとドキッとしつつも話しやすい店員さんで、ミルクティーにしやすい茶葉と、
水出しでも飲みやすいグリーンルイボスを買った。
こういうとき、私は本当は気になるけれど、店員さんを避けたり、
こんなおしゃれは自分にはと敬遠して、入っていないだけなのかもしれないなと感じる。
押し売りでも、気を使って買ったわけでもない。
店員さんと話して、緊張も和らいで、知らないことを少し聞いてみて、
それも面白いな、いいなと納得して買い物をした。なんだか豊かな体験だった。
飲み物は好きだ。コーヒーも、お茶も、ココアも、炭酸も、ジュースも好きだ。
なぜだろう。音なのか、味なのか、その空間か、体験か。
食べ物が消費されていくのに対し、私にとっての飲み物は吸収されていくような感じがする。
喉を通る感覚なのか、グラスの中身が減っていく分、自分に流れ込む感覚なのか。
暑くてのどがカラカラになったとき、やっと飲み物を口にすると、
「生き返る」「染み渡る」と感じることがあると思う。
飲み物を飲むこと全般に対して、ああいう感覚を持っているのかもしれない。
ゲームのポーションのような、自分を元気にしてくれるもの。
きっとお酒を飲めたらもっと楽しかっただろう。でも私にはこれでちょうどいい。
酒を飲み交わすコミュニケーションも駆け引きもできない不器用さが自分らしい。
ブログを書きたい。と思うのは、
今日何があった?と誰かに聞いてほしいと思っているからかもしれない。
ただ感動する出来事を、写真や絵日記のように残しておきたいからブログにするときもある。
けれどそこまで大きな感情が動いていなくても、ブログを書きたくなることが多い。
「今日はどんなことがあった?」
「元気ないね。何かあった?」
「もっと〇〇のいろんな話を聞きたいな」
そうやって気にかけてもらうことが、私は昔からなかった。
私は話を聞く役割だった。自分が話せば「疲れる」「ネガティブだからそうなるんだ」と母に言われることが多かった。
学生時代もどちらかというと聞く役割だった。
人と違うことや手に入らないものも多かったし自分のことを言うのは恥ずかしかった。
家族の悩みを友達に言うのは重いととられるのだとも察していたし家のことも徐々に自分の中に秘められていった。
話したい、というよりは聞いてほしい。なんだと思う。
だから聞き手からしたら少し重かったのは事実かもしれない。一緒に楽しくなる話ではなかったから。
今もずっと聞いてほしいんだ思う。
今日どんなことがあったか、どんなふうに思ったか、
どういうことがうれしくて、どんなことがいやだったか。
やってみてどうだったか、落ち込んだのは、本当に落ち込んだだけだったか。
もう辞めたいというけれど、本当はどうしたいのか。
学生時代に先生が話を聞いてくれたように、
私の話を、私の一日を、私の気持ちを気にかけてくれる人が欲しかった。
だから私にブログはあっていると思う。
もともとの性格的にも内向的で自分との対話が多い。抱え込むとパンクする。
自分の話を吐き出すと同時に、受け止めることもできるブログは私にとって心地がいい。
私の気持ちを、まだ上手には肯定できなくても、
少なくとも私の気持ちの存在を肯定することができる。
何度か転職しているが、自分が自分の気持ちを吐き出す方法を持っていれば、
あるいは職場の誰かに、聞いてもらうことができれば、そういう関係をわたしが構築できれば、
今までいた会社を離れなくても済んだかもしれない。
そのくらい、今までの苦しみは特定の現象・事実よりも自分の感情が居場所を失ったことで発生していたように思う。
意見や主張としてではなく、ただ感じたことを、
ジャッジせずに受け止めてくれる人がいたら、どれだけ気持ちが軽かっただろう。
つらいよーとか、いやだよーとか、
もうあの人と仕事したくないよとか、うまくいかないよーとか、
自分的にはうまくできた!とか、ここを頑張ったんだよとか、子供みたいに言いたい。
子供の頃に言えなかったから、消化されずに残ってしまった思い。
それは持っていい感情なんだよと、くだらなくなんてないよと
自分で言ってあげることができるようになれば、私の人生はもう少し明るいものになると思う。
我ながら、脈絡もない、読者として読んでいたらたぶんよくわからないし面白くもなさそうなブログだが、
これを書くことでどのくらい救われているかわからない。
今までは、できない自分をそのままブログに書いたとして、
それはできない自分を受け入れるという体をとりながら、むしろ自分を貶める行為になっていた。
スキーマ療法のワークを行っているのが、すごくいい方に働いたと思う。
自分の気持ちをあまりジャッジしなくなった。ただ、こういう感情を持った。という事実に目を向けて、
ただ受け止めて、ブログに書いて数日後に、ああそういえばこうだったのかもしれないなと、
新しい解釈が浮かんだりした。それは、なぜそんな感情を持ったのかの原因究明ではなくて、
その感情の後ろにいる、隠れている感情に気づいてあげられるようになったということだ。
なぜ、どうして、じゃない。
あの感情は怒りよりもこういう言葉がより近いかもしれない、同時にこれもいたかもしれない、という感じ。
自分の心の動きをただ観察して、気付いた感情にそうだったんだねと理解を示す。
その感情が望ましくないから消すのではなく、望ましくないな、と感じているということも俯瞰してみる。
子供の頃、私がしてほしかったのも多分そういう話の聞き方だったのだろうな。
カウンセリングでも、それ以外の場面でも、
自分が誤解されるのを避けるために、悪い子だと思われないための言い訳のように、
〇〇なわけでもないんですけど、と保険をかけたり(このブログでもよくやってる)
場面を必要以上に解説したりしている。これは、ある程度自覚がある。
話があまりうまくないというそもそもの原因と、
思考や感情が忙しくてパニック気味になっていることと、
上に書いたように「誤解される」「悪い子だと思われる」…言い方を変えれば
相手が自分を理解するとは思っていない、信用していないのだと思う。
だから事細かく話す時ほど、多分否定を恐れている。人の判断を恐れている。
相手にどうか味方になってほしいと切望している。
ひょっとすると、いい話の時(うれしかった、楽しかった)は、より聞いてほしいと思っているし
悪い話(悲しかった、むかついた、苦しかった)は、その感情を否定しないでほしいと思っている
と言うふうにものによって違っているかも。
だっていい話の時は言い訳の必要がないから。
そして自分から言わなければ、聞いてもらえない話でもあった。「よかったね」で片付けられるのが、自分の話にすり替えられるのが悲しいから、全部聞いてほしいと願っている。
悪い話は一蹴されてしまえば終わり、覆らない。お前が悪い、こうすればいい(のにしないのが悪い)そういうメッセージを感じてしまうから、否定されるのが怖い。自分は悪くないんだと、できることはしたし、避けられなかったんだと、あらかじめ弁明をしないと不安で仕方がない。
できない自分でいてはいけない、人に見せてはいけない。自分一人でなんとかしなくてはいけない。
そういう切迫した思いが少なからずあるように思う。
こうして書いているとやはり涙が出てきてしまう。
でもこうやって気づくことができたのなら、これから少しずつ何か変わっていくと信じたい。
ブログを書いたりスキーマ両方のワークをしたりしてせめて自分が自分の味方であれるように。